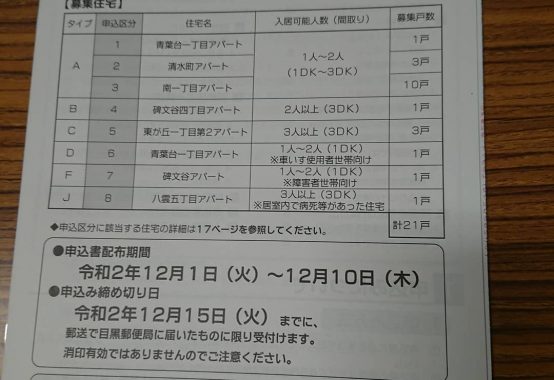遅まきながら、今般の台風と地震にて被災された皆様のご心中をお察し致しますとともに、犠牲になられました尊い命のご冥福をお祈り致します。そして、一日でも早くの復旧・復興を願うものであります。
アメリカの同時多発テロから17年が経ちました。同時に、あのテロで犠牲になった3000名にも及ぶ人々のご冥福を再度、お祈り致します。私事、毎年この日には周辺当事者としての記憶が蘇るものです。備忘録までに、記憶の断片をこの機会に残しておこうと思いました。
さて、あの時の私は28歳になりたてで、米国での学生を始めたばかりの頃でした。まだ慣れない英語のTVニュースでその歴史的惨事の何となく概要を理解し、すぐにスーパーマーケットに向かいコメと油とトイレットペーパーを買い出しに行きました。祖父母の経験としての耳学問をしていたからなのでしょうか、何かがあればすぐ家庭内の食糧の備蓄をするものだと、思い込んでいたのかもしれません。(NYCの凄かった事は物流が止まったのは1週間程度であった事だと思います。それより山積みのゴミとそれに群がるネズミの方が問題になった様な記憶があります。)ハーレムに住む私の近隣住民のほとんどは黒人でしたが、近隣の皆さんは買い出し等には行かないで、落ち着いているというよりは、妙に上がったテンションで道で盛り上がっていたのが印象的でした。
外に出てみると北側からセントラルパーク越しに見えるミッドタウンの上空は、ダウンタウンからの灰色の煙で覆われ、何だか嫌な気分がしたものです。電話も携帯も不通で、かろうじて生きていたインターネットで日本の家族や友人には安全であるとの連絡を取りました。不思議と地下鉄はまだ動いていたのですが、大学に行く気にもなれずにただ、ラジオをつけっぱなしにして胸騒ぎに耐えながら1日過ごしていた様な気がします。また、何か出来る事をしに手伝いに行く事より、状況を把握する事の方が先だと思ったのでしょう。或いは、生命に関わるかもしれないと感じる状況下においては下手に動くより、大人しく状況が好転するのを待つ方が得策だと本能的に悟っていたのかもしれません。一方で、町全体が節電しながらも、まだブロードウェイ沿いのレストランやカフェは営業をされていたのが印象的でした。夜のニュースでマンハッタンから、ハイヒールを脱いで裸足で血を流しながら歩いて橋を渡って帰宅する女性の映像を見て、同じ現実の中で対比する形の出来事の中に、自分も参加している事を上手く認識する事が出来ませんでした。
(以下、思い出しながらの執筆都合につき調変します。)
恐らく翌日位だったか、公共放送のラジオからは「輸血の為のO型他の血液が足りない!14thストリートの○○病院に献血に来て欲しい。」との悲痛なアナウンスが繰り返し流れてきたので、僕は行く事にした。その頃にはバスも地下鉄も止まり、道路も封鎖の上、動く車両は救急と消防、警察に州兵、軍だけに制限されていた。勿論、飛行機も飛んでいない。緊急車両が通る都度、道行く人々はその車両に乗車している、これから現場で戦いに行く公務のヒーロー達を拍手喝采で送り出す事度々であった。僕はやっと事の重大性を理解し、この度の事象がボランティアや手伝いをしに現場へ行くなんてレベルのものでは無かった事を意識していった。
3時間程歩いたのだろうか、ラジオで言っていた病院に着いたのは良いけれど、今日はオーバーキャパだから明日また来て欲しい等と門前払いされる始末にて、再度ラジオを聞いたら今度はO型じゃない血液が足りないと言っており、来た道をまたトボトボと歩いて帰り、1日がそんなので終わってしまった。
そのまた翌日、今度は早朝に病院に行った僕は無事献血をする事が出来た。しかし、当時体重60キロ位しかない、米国では小柄な僕から、1パイント約500ミリリットルもの血液を抜いて下さり、そのまま意識不明の貧血で倒れた。おまけに出ない血を無理やり出す為に、握り健康器具でグーパー、グーパー、絞り出す側の手で反復運動させられるオマケまでつけられてしまっていた。倒れる直前に、うっすらと500と書かれた血の袋に僕の体から絞り出した血が、たわわに実る果実の様にぶらぶら溜まってゆくのを見て気持ち悪いと思ったのが最後の記憶だった。病院から出てこれたのは夜6時をまわってからだった。ほぼ一日、病院に居たことになる。2次災害だった。出血多量だったせいか、外に出たらまだ秋口であるにもかかわらず、ガタガタと震え上がるほどに寒かったのを覚えている。そんな状況下の中、「よく戦争の映画で出血多量の重症の人間が寒いと言って死んでゆくのは、こういう感覚なのではないかな、、」と思っていた。その後どうやって帰ったのか全く覚えていないが、友達が付き添ってくれたのだけ覚えている。という事は、携帯も頃合いによっては使えたのだろう。
やがて、アメリカ合衆国は報復としてのアフガニスタン紛争とイラク戦争に突入してゆくのだが、その戦争当事者国に住む一個人としては、やはりイビツな感覚や出来事を町の端々で垣間見る様になった。社会の少数民族への無知と疑心暗鬼からの、頭から頭巾(ブルカ)をかぶるイスラム教徒への露骨な嫌がらせや、モスクへの投石や封鎖などの迫害である。アメリカという地域社会が、全体主義と右傾化に極度に傾いてゆき、その反動なのか、傾いた側にある安全に生きるコミュニティー内での気持ちの悪い程の仲間意識と干渉主義と笑顔であった。何故だかそのコミュニティーの片隅に存在する事を許されたアジア人留学生の僕は、その居心地の悪い仲間内の笑顔の交換会を好きになれなかった。恐らくそのコミュニティーの中での慈悲を向けるべく弱者であると勝手に認識されていたのだろうか。その反面で日米の近代史にはあったものの、何時か何処かのタイミングで僕ら黄色人種も異端や異国民と認識される事があるのかもしれない、という不安には駆られなかった。
半年後なのか、1年位後なのであろうか、NY市長の名前で先の献血へのヒーロー扱いでのお礼状が届いたのには大変嬉しく、大事にその手紙を取っておいたのであるが。奇しくも世は報復戦争に突入してゆく前夜であった事とは、無関係のものと理解しておきたいと思っていた。
もう一つ、強烈に覚えているのは、地下鉄が動き出してから間もなくの頃であったと思う。何らかの原因で乗っている地下鉄が止まり、乗っているその車両の電気も消え、その車両が集団パニックを起こした事である。よく考えれば隣の車両は電気がついていたにも関わらず、誰かが起こしたパニックがその周りの人々に伝播し、車両中なの一部なのか分からないが、真っ白な恐怖の淵に引きずりこまれて行ったのである。気が付いた時、黒人のおばさんに「Are you OK?」と車両でしゃがみ込み意識を失う僕は肩を叩かれていた。以来、僕は閉所恐怖症になってしまった。地下鉄やエレベーターに乗るのが苦手になり、通学は1時間かけて歩いて通うようになった。